明けましておめでとうございます。
新年1発目はノグッチャンの担当です。
みなさん、年末年始は有意義にすごせたでしょうか?
私は・・・
「食う・寝る・遊ぶ」で終わってしまいました。
年始早々、反省しております。
さて昨年の続きになりますが
『熱拡散率の測定において、黒化膜があたえる影響』
について、検証していきましょう!
用意した試料は、以下の4種類。
―――――――――――――――――――
材料名 熱拡散率 [×10-6m2s-1]
―――――――――――――――――――
銅(Cu) 117
タンタル(Ta) 24.6
SUS 4.05
ホウケイ酸ガラス(Pyrex) 0.6
―――――――――――――――――――
銅(Cu)とタンタル(Ta)についての検証は終わりましたね。
<参考>
銅(Cu) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52008454.html
タンタル(Ta) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52023450.html
次は、SUSの黒化膜の影響を調べていきたいと思います。
では、実験を始めましょう。
今回使用するSUSの試料厚みは、100μmです。
このSUSを黒化していきます。
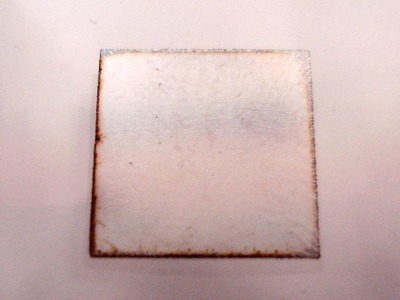
下の画像は黒化後のSUS。

熱拡散率の測定をしてみましょう。
※ いつものように、熱拡散率の測定にはサーモウェーブアナライザTA3を使用しました。
測定してみると、
熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値に比べると1.2%程度低いですが、測定誤差の範囲内でしょう。
ここからは前回と同じ作業です。
地道に、
黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ⇒ 黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ・・・・・・・・と。
またあの作業か
と思った矢先に、アノ言葉が頭によぎりました。
『熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』
ということは
黒化膜をかなり厚めに塗らないと、影響が出ないんじゃないか?
これは長期戦かっ!
・・・と考えているとやる気を無くしそうなので、とにかくやってみましょう。

――― 実験中 ―――
測定結果は・・・
黒化膜が約1μmのときに、熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.2%
黒化膜が約2μmのときに、熱拡散率:4.02 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-0.7%
黒化膜が約3μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.5%
黒化膜が約4μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.5%
ん~、あまり変化が見られず。
このままじゃ長期戦に・・・ってことで、黒化膜の間隔を倍にします。

↑ 冗談です。真似しないでください。
悪ふざけはやめて実験再開です。
黒化膜が約6μmのときに、熱拡散率:3.98 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.7%
黒化膜が約8μmのときに、熱拡散率:3.86 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-4.7%
ここでようやく違いが見えてきましたね。
あともう少し♪
――― 継続して実験中 ―――
黒化膜が約10μmのときに、熱拡散率:3.78 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-6.7%
黒化膜が約12μmのときに、熱拡散率:3.56 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-12.1%
文献値から、10%以上も低くなってしまいました。
もう限界ですね。
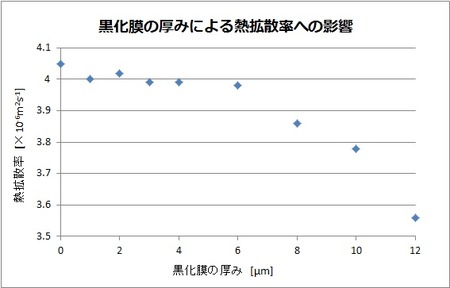
上記結果から
SUSは厚さの10%を超えたあたりから、黒化膜で10%以上の影響が出てくることが分かりました。
『「熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』
も実証出来ているし、実験成功です。
ということで
今回の検証はここまで。
後日、最後の試料(ホウケイ酸ガラスPyrex)の検証をしていきたいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。
以上
(著:ノグッチャン)
新年1発目はノグッチャンの担当です。
みなさん、年末年始は有意義にすごせたでしょうか?
私は・・・
「食う・寝る・遊ぶ」で終わってしまいました。
年始早々、反省しております。
さて昨年の続きになりますが
『熱拡散率の測定において、黒化膜があたえる影響』
について、検証していきましょう!
用意した試料は、以下の4種類。
―――――――――――――――――――
材料名 熱拡散率 [×10-6m2s-1]
―――――――――――――――――――
銅(Cu) 117
タンタル(Ta) 24.6
SUS 4.05
ホウケイ酸ガラス(Pyrex) 0.6
―――――――――――――――――――
銅(Cu)とタンタル(Ta)についての検証は終わりましたね。
<参考>
銅(Cu) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52008454.html
タンタル(Ta) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52023450.html
次は、SUSの黒化膜の影響を調べていきたいと思います。
では、実験を始めましょう。
今回使用するSUSの試料厚みは、100μmです。
このSUSを黒化していきます。
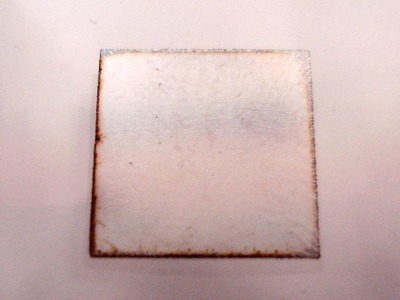
下の画像は黒化後のSUS。

熱拡散率の測定をしてみましょう。
※ いつものように、熱拡散率の測定にはサーモウェーブアナライザTA3を使用しました。
測定してみると、
熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値に比べると1.2%程度低いですが、測定誤差の範囲内でしょう。
ここからは前回と同じ作業です。
地道に、
黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ⇒ 黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ・・・・・・・・と。
またあの作業か
と思った矢先に、アノ言葉が頭によぎりました。
『熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』
ということは
黒化膜をかなり厚めに塗らないと、影響が出ないんじゃないか?
これは長期戦かっ!
・・・と考えているとやる気を無くしそうなので、とにかくやってみましょう。

――― 実験中 ―――
測定結果は・・・
黒化膜が約1μmのときに、熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.2%
黒化膜が約2μmのときに、熱拡散率:4.02 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-0.7%
黒化膜が約3μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.5%
黒化膜が約4μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.5%
ん~、あまり変化が見られず。
このままじゃ長期戦に・・・ってことで、黒化膜の間隔を倍にします。

↑ 冗談です。真似しないでください。
悪ふざけはやめて実験再開です。
黒化膜が約6μmのときに、熱拡散率:3.98 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-1.7%
黒化膜が約8μmのときに、熱拡散率:3.86 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-4.7%
ここでようやく違いが見えてきましたね。
あともう少し♪
――― 継続して実験中 ―――
黒化膜が約10μmのときに、熱拡散率:3.78 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-6.7%
黒化膜が約12μmのときに、熱拡散率:3.56 [×10-6m2s-1](3回平均)
文献値との差:約-12.1%
文献値から、10%以上も低くなってしまいました。
もう限界ですね。
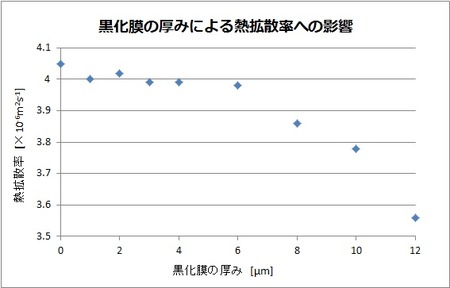
上記結果から
SUSは厚さの10%を超えたあたりから、黒化膜で10%以上の影響が出てくることが分かりました。
『「熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』
も実証出来ているし、実験成功です。
ということで
今回の検証はここまで。
後日、最後の試料(ホウケイ酸ガラスPyrex)の検証をしていきたいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。
以上
(著:ノグッチャン)
